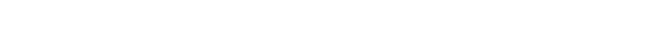正倉院関連年表
凡例
- 事項中の用字は典拠史料に従うのを基本としたが、必要に応じて改めた場合がある。
- 典拠史料が多数に及ぶ際は、代表的なもののみを掲出した場合がある。また明治以降については掲出を省略した。
- 典拠史料のうちいくつかは略名で表記した。それぞれの略名と正式名称は以下の通り。
続々修□ノ◯=続々修正倉院古文書第□帙第◯巻、続修後集□=続修正倉院古文書後集第□巻、東南院□ノ◯=東南院古文書第□櫃第◯巻、塵芥□=正倉院塵芥文書第□巻、実祐記=慶長十九年東大寺三蔵開封記(薬師院実祐記)
奈良時代
| 西暦 | 和暦 | 月日 | 事項(〔〕内は典拠史料) |
|---|---|---|---|
| 743年 | 天平15年 | 10月15日 | 聖武天皇、紫香楽宮において、大仏造立の詔を発する〔『続日本紀』同月辛巳条〕 |
| 749年 | 天平勝宝元年 | 7月2日 | 聖武天皇、譲位し、孝謙天皇、即位する〔『続日本紀』同月甲午条〕 |
| 752年 | 天平勝宝4年 | 4月9日 | 東大寺大仏の開眼供養が催される。孝謙天皇、百官人を率いて参列〔『続日本紀』同月乙酉条〕。聖武太上天皇と光明皇太后も臨席〔『東大寺要録』供養章〕 |
| 756年 | 天平勝宝8歳 | 5月2日 | 聖武太上天皇、崩じる〔『続日本紀』同月乙卯条〕 |
| 6月21日 | 光明皇太后、聖武の七七忌にあたり、国家の珍宝と60種の薬物を東大寺大仏に献納する〔国家珍宝帳、種々薬帳〕 | ||
| 7月26日 | 屛風や花氈などが東大寺に献納される〔屛風花氈等帳〕 | ||
| 10月3日 | 宝庫より人参が出蔵され、施薬院に充てられる〔出入帳〕 ※最初の出蔵 | ||
| 757年 | 天平勝宝9年 | 正月21日 | 宝庫より沙金が出蔵され、大仏鍍金料として造東大寺司に充てられる〔沙金桂心請文、出入帳〕 |
| 5月2日 | 聖武太上天皇の一周忌法要が東大寺において営まれる〔『続日本紀』同月己酉条〕 | ||
| 天平宝字元年 | 閏8月24日 | 金薄絵木鞘大刀子と人勝が献納される〔斉衡三年雑財物実録〕 | |
| 758年 | 天平宝字2年 | 6月1日 | 王羲之と王献之の真跡書が東大寺に献納される〔大小王真跡帳〕 |
| 10月1日 | 光明皇太后、父の藤原不比等から継承した真跡屛風を東大寺に献納する〔藤原公真跡屛風帳〕 | ||
| 12月16日 | 宝庫より冶葛が出蔵され、内裏に進上される〔出入帳、延暦六年曝涼使解〕 | ||
| 759年 | 天平宝字3年 | 3月25日 | 宝庫より桂心100斤が出蔵され、施薬院に充てられる〔沙金桂心請文、出入帳〕 |
| 4月29日 | 宝庫の花氈が、宮中御斎会の堂装束のために貸し出される〔出入帳、延暦六年曝涼使解〕 ※薬物・沙金以外の最初の出蔵 | ||
| 12月26日 | 宝庫より犀角奩や陽宝剣、陰宝剣などが出蔵される〔出蔵帳〕 | ||
| 760年 | 天平宝字4年 | 6月7日 | 光明皇太后、崩じる〔『続日本紀』同月乙丑条〕 |
| 761年 | 天平宝字5年 | 3月29日 | 宝庫より麝香、犀角など多種多量の薬物が出蔵され、内裏に進上されたほか、僧や諸人の施薬料に充てられる〔出入帳、延暦六年曝涼使解〕。また、同日、宝庫の薬物のうち甘草、大黄、人参、桂心の各1唐櫃分を中倉に移す〔出入帳〕 |
| 762年 | 天平宝字6年 | 12月14日 | 宝庫より欧陽詢の真跡屛風が道鏡に貸し出される。2年後の8年7月27日、返納〔出入帳〕 ※宮中以外への最初の出蔵 |
| 764年 | 天平宝字8年 | 7月27日 | 宝庫より桂心が出蔵され、施薬院に充てられる〔出入帳、雑物出入継文〕 |
| 9月11日 | 宝庫より御大刀48口、黒作大刀40口、弓103枝、甲100領、靫3具、胡禄96具が出蔵され、内裏に献じられる〔出入帳、延暦六年曝涼使解〕。この日、藤原仲麻呂の乱が勃発〔『続日本紀』同月乙巳条〕 | ||
| 767年 | 天平神護3年 | 2月4日 | 称徳天皇、東大寺に行幸する。このとき銀壺などを献納する〔『続日本紀』同月甲申条、銀壺(南倉)〕 |
| 768年 | 神護景雲2年 | 4月3日 | 称徳天皇、東大寺に行幸し、碧地彩絵几などを献納する〔同附茶綾几褥(中倉)〕 |
| この年の5月13日付、称徳天皇願文を持つ『大乗悲芬陀利経』巻第三などの経典4巻が、聖語蔵に伝わる | |||
| 770年 | 神護景雲4年 | 5月9日 | 宝庫より屛風3帖が出蔵され、造東大寺司に充てられる。2年後の宝亀3年8月28日、返納〔出入帳〕 |
| 8月4日 | 称徳天皇、在位のまま崩じる〔『続日本紀』同月癸巳条〕 | ||
| 776年 | 宝亀7年 | 9月21日 | 宝庫の大刀が点検される〔延暦六年曝涼使解〕 |
| 778年 | 宝亀9年 | 5月18日 | 宝庫より螺鈿紫檀琵琶と紫檀琵琶が出蔵され、内裏に献上される。翌年12月6日、返納〔出入帳〕 |
| 779年 | 宝亀10年 | 12月6日 | 宝庫より冶葛が出蔵される。親王禅師(早良親王)の請いによる〔出入帳、雑物出入継文〕 |
| 781年 | 天応元年 | 8月12日 | 宝庫より王羲之と王献之の真跡書1巻、王羲之の「書法」20巻、及び『雑集』・『楽毅論』など「御製書」4巻が出蔵され、内裏に進上される〔出入帳〕 |
| 8月18日 | 宝庫より出蔵されていた「書法」のうち12巻と「御製書」4巻が返納される〔出入帳〕。またこの日、宝庫より桂心、人参、芒硝、呵梨勒等が出蔵され、造東大寺司に(一部、施薬院にも)充てられる〔出入帳、雑物出入継文、延暦六年曝涼使解〕 | ||
| 782年 | 天応2年 | 2月22日 | 宝庫より出蔵されていた王羲之と王献之の真跡書1巻が返納される〔出入帳〕 |
| 784年 | 延暦3年 | 3月29日 | 宝庫より出蔵されていた王羲之の「書法」8巻が返納される〔王羲之書法返納文書、出入帳〕 |
| 787年 | 延暦6年 | 6月 | 宝物の曝涼と点検が行われ、26日付で報告書が作られる〔延暦六年曝凉使解〕 |
| 793年 | 延暦12年 | 6月 | 宝物の曝涼と点検が行われ、11日付で報告書が作られる〔延暦十二年曝凉使解〕 |
平安時代
| 西暦 | 和暦 | 月日 | 事項(〔〕内は典拠史料) |
|---|---|---|---|
| 794年 | 延暦13年 | 4月27日 | この日の官符により、宝庫より麝香、犀角等の薬物が出蔵され、内裏に進められる〔延暦十二年曝凉使解、弘仁二年勘物使解〕。また、同日付の別の官符により、宝庫より大黄が出蔵され、藤原内麻呂と菅野真道に給される〔弘仁二年勘物使解〕 |
| 6月13日 | この日の官符により、宝庫より檳榔子が出蔵され、内裏に進められる〔弘仁二年勘物使解〕 | ||
| 9月13日 | この日の官符により、宝庫より呵梨勒が出蔵され、内裏に進められる〔弘仁二年勘物使解〕 | ||
| 799年 | 延暦18年 | 11月11日 | 宝庫より大黄、甘草、小草、檳榔子等の薬物が出蔵され、内裏に進められる〔雑物出入継文、弘仁二年勘物使解〕 |
| 802年 | 延暦21年 | 11月21日 | 宝庫より大黄、甘草等の薬物が出蔵され、内裏に進められる〔雑物出入継文、弘仁二年勘物使解〕 |
| 803年 | 延暦22年 | 1月23日 | 宝庫より大黄等の薬物が出蔵され、病僧の施薬料として東大寺三綱に充てられる〔雑物出入継文、弘仁二年勘物使解〕 |
| 805年 | 延暦24年 | 11月15日 | 宝庫より﨟蜜が出蔵され、東大寺大仏背後の山形を彩色する料などとして、造寺所に充てられる。また、桂心、甘草が出蔵され、病僧の施薬料として東大寺三綱に充てられる〔雑物出入継文、弘仁二年勘物使解〕 |
| 806年 | 大同元年 | 9月7日 | 宝庫より白犀角が出蔵され、内裏に進められる〔雑物出入継文、弘仁二年勘物使解〕 |
| 811年 | 弘仁2年 | 9月 | 宝庫内の資財と官物の点検が行われ、25日付で報告書が作られる〔弘仁二年勘物使解〕 |
| 813年 | 弘仁4年 | 2月9日 | 宝庫より犀角が出蔵され、藤原緒嗣に売却される〔御物納目散帳〕 ※売却の初例 |
| 814年 | 弘仁5年 | 6月17日 | 宝庫より麝香、犀角が出蔵され、内裏に進められる。麝香は7月29日に返納〔雑物出入帳、御物納目散帳〕 |
| 7月26日 | 宝庫より黄袷、紫綾、竜頭、仏台幡を出蔵し、東大寺の寺用に充てる旨の申請がある〔同日東大寺三綱牒(続々修四十四ノ十一)〕 | ||
| 7月29日 | 宝庫より桂心、人参、胡枡等の薬物が出蔵され、病僧の施薬に充てられる〔雑物出入帳、御物納目散帳〕 | ||
| 9月17日 | 宝庫より屛風36帖と白石鎮子16枚が出蔵され、売却される〔雑物出入帳〕 | ||
| 10月19日 | 宝庫より銀平文琴、漆琴、玳瑁箸が出蔵され、売却される〔雑物出入帳〕 | ||
| 817年 | 弘仁8年 | 5月27日 | 宝庫より弘仁5年10月に出蔵された琴と箸の代替として、金銀平文琴1隻、漆琴1隻、箸2隻が納められる〔雑物出入帳〕 |
| 820年 | 弘仁11年 | 10月3日 | 宝庫より王羲之と王献之の真跡や繡線鞋などが出蔵され、売却される〔雑物出入帳〕 |
| 822年 | 弘仁13年 | 3月26日 | 宝庫より鏡5面、浅香、紫鉱等が出蔵され、仏事用に充てられる〔雑物出入帳、御物納目散帳〕 |
| 5月6日 | 宝庫より甘草、人参等の薬物が出蔵され、病僧の施薬に充てられる〔雑物出入帳〕 | ||
| 823年 | 弘仁14年 | 2月19日 | 宝庫より桐木箏、紫檀琵琶、螺鈿紫檀五絃琵琶、新羅琴2面、銀平文革筥等が出蔵される。4月14日に返納されたが、新羅琴2面、桐箏、紫檀琵琶は代替品が納められ、革筥は返納されず〔雑物出入帳〕 |
| 826年 | 天長3年 | 9月1日 | 宝庫より甘草、人参等の薬物が出蔵され、病僧の施薬に充てられる〔雑物出入帳〕 |
| 832年 | 天長9年 | 5月25日 | 宝庫より薫陸、雑香が出蔵され、大仏殿読経所の料に充てられる〔同日出用注文(続修後集四十一)〕 |
| 856年 | 斉衡3年 | 6月 | 宝庫内の財物の点検が行われ、25日付で報告書が作られる〔斉衡三年雑財物実録〕 |
| 860年 | 貞観2年 | 8月14日 | 宝庫より紫鉱が出蔵される〔御物納目散帳〕 |
| 919年 | 延喜19年 | 4月 | 宝庫より力士装束が出蔵される。天暦9年(955)4月8日、返納〔呉楽力士裹(南倉)〕 |
| 950年 | 天暦4年 | 6月 | 南倉に、東大寺羂索院双倉の品が移納され、綱封とされる〔『東大寺要録』諸院章〕 |
| 971年 | 天禄2年 | この年の5月17日に東大寺別当となった法縁、2年間で「正蔵院」を含む多数の堂舎を修造する〔天延二年五月二十四日太政官牒(東南院一ノ二)〕 | |
| 1019年 | 寛仁3年 | 9月30日 | 藤原道長、宝庫を開き、宝物を取り出させて見る〔『左経記』同日条、『小右記』同月二十九日条〕 |
| 1031年 | 長元4年 | 7月5日 | 仁海僧都、宝庫が強風により破損したことを報告し、修理を請う〔『小右記』同日条〕。これを受け、翌年8月4日以前に修理が実施される〔『左経記』同年八月四日条〕 |
| 1038年 | 長暦2年 | 3月3日 | 夜、勅封蔵に盗人が入り、宝物が盗み取られる〔『東大寺別当次第』〕 |
| 1040年 | 長暦4年 | 9月18日 | 前年3月に起きた勅封倉盗難事件の犯人(僧の長久と同類数名)が捕らえられる〔『春記』同月二十四日条〕。犯人より押収した百余両に及ぶ銀は、この年のうちに勅封倉へ戻される〔『春記』同年十月十八日条、檜合子蓋(南倉)〕 |
| 1057年 | 天喜5年 | 正月 | 「正蔵院南御庫」(南倉)が修理され、8〜10月頃、「勅封御庫」(北倉・中倉)の棟1間分が葺き替えられる〔天喜五年東大寺修理所注進文(東南院二ノ三)〕 |
| 1079年 | 承暦3年 | 8月28日 | 勅封蔵北西隅の破損部を修理するため、宝庫が開かれることになり、朝廷から使者を派遣するとの連絡が東大寺に出された〔同日官宣旨〕。このとき宝庫から麝香5両が内裏に進上され、代わりに銀提子1口(南倉)が施入された〔『東大寺別当次第』〕 |
| 1100年 | 康和2年 | この年の冬、勅封蔵が修理される〔『東大寺別当次第』〕 | |
| 1116年 | 永久4年 | この年、南倉の納物のうち、「重物」(重要なもの、の意か)を勅封倉に移す〔綱封蔵見在納物勘検注文(塵芥十八)〕 | |
| 1117年 | 永久5年 | 8月7日 | 綱封蔵(南倉)の納物が調査され、目録が作られる〔綱封蔵見在納物勘検注文(塵芥十八)〕 ※南倉宝物にかかわる初めての目録 |
| 9月23日 | 綱封蔵(南倉)より大仏殿所用具のために出蔵された銀、銅等の斤量が報告される〔綱封蔵銀銅等斤納注文案(塵芥二十三)〕 | ||
| 1130年 | 大治5年 | 5月1日 | 勅封倉を開き、東大寺別当の定海が立ち会って、点検が行われる。湿損の疑いによる〔『中右記』同日条、御物納目散帳〕 |
| 1142年 | 康治元年 | 5月6日 | 鳥羽法皇、勅封倉を開き、聖武天皇の玉冠、鞍、碁局、投壺など数々の宝物を見る〔『本朝世紀』同日条〕 |
| 1150年 | 久安6年 | 3月17日 | 綱封蔵(南倉)下階に、平忠盛が東大寺に施入した蒔絵野剣、丸鞆犀角帯などを納める。これらは、忠盛の息子でその1年前に没した家盛の遺品であった〔綱封蔵雑物入出帳(塵芥十六)〕 |
| 1160年 | 永暦元年 | 2月8日 | 綱封蔵より火舎、磬、伎楽面などが出蔵され、東大寺の仏事等に充てられる。あわせて平家盛の帯も出蔵〔綱封蔵雑物出蔵帳(塵芥三十六)〕 |
| 1161年 | 永暦2年 | 正月30日 | 綱封蔵より釘、銅等が出蔵され、東大寺大仏殿華厳会に使用する仏具等の修理料に充てられる〔綱封蔵雑物入出帳(塵芥十六)〕 |
| 1165年 | 永万元年 | 7月22日 | 六条天皇の即位式を目前に控え、綱封蔵の礼服を取り出して内裏に進めるため、僧綱から使者を遣わすことが東大寺に伝えられる〔同日僧綱牒(東南院四附ノ三)〕 |
| 1167年 | 仁安2年 | 3月5日 | 綱封蔵より宝鐸、鉢などが出蔵され、東大寺南大門での使用に充てられる。あわせて平家盛の剣も出される〔綱封蔵雑物入出帳(塵芥十六)〕 |
| 1170年 | 嘉応2年 | 4月20日 | 後白河法皇、南都へ行幸の折、勅封蔵を開いて宝物を見る。平清盛等も同行〔『兵範記』同日条〕 |
| 1180年 | 治承4年 | 12月28日 | 平重衡の軍により南都が焼きはらわれる。東大寺と興福寺は壊滅的な被害が出るも、宝庫は難を逃れる〔『山槐記』同日条ほか〕 |
鎌倉時代
| 西暦 | 和暦 | 月日 | 事項(〔〕内は典拠史料) |
|---|---|---|---|
| 1185年 | 文治元年 | 8月28日 | 後白河法皇、再興された東大寺大仏の開眼供養にあたり、前日に勅封倉より出蔵した開眼筆と墨を使い、自ら筆を入れる〔『東大寺続要録』供養篇、『玉葉』同月二十九日条、『山槐記』同日条〕 |
| 11月15日 | 綱封蔵の階下を重源上人に開け渡すため、経論431帙を他の経蔵に移し、それ以外の唐櫃等を階上に納める〔綱封蔵取出聖教注文(塵芥二十三)〕 | ||
| 1189年 | 文治5年 | 3月21日 | 勅封倉を開いて点検するため、造東大寺長官の藤原定長が東大寺へ下向する。これより先、宝庫の湿損甚大なることが東大寺から報告されたのを受けて〔『玉葉』同日条〕 |
| 1193年 | 建久4年 | 5月10日 | 勅封倉の破損状況が、去る5日に南都へ下向し点検を行なった藤原定長より報告される〔『玉葉』同日条〕 |
| 8月25日 | 勅封蔵が修理のために開かれる。宝物は、運び出して点検した後、綱封蔵(南倉)に仮置される。このとき作られた宝物目録が残る。修理は翌年3月までに完成し、宝物も戻される〔『東大寺続要録』宝蔵篇〕 | ||
| 1198年 | 建久9年 | 2月26日 | 宝庫より礼服を取り出すため、勅使が下向する。翌27日、土御門天皇即位の料として白練絹礼服、練綾礼服、玉冠が出蔵され、夜に入って京都に届く〔『三長記』同月二十六・二十七・二十八日条〕 |
| 1230年 | 寛喜2年 | 7月17日 | 北倉と南倉が修理のために開封される。北倉の宝物は中倉へ移され、南倉の納物は東大寺上司倉3宇のうちの1宇に仮置される〔『東大寺続要録』宝蔵篇〕 |
| 10月27日 | 中倉に盗人が入り、宝物が盗み取られる。11月29日、僧の顕識が犯人として捕らえられる。自供により、転売目的で盗んだ鏡8面は、思うような値が付かず、砕き割って大仏殿前の社に捨て置いたことが判明〔『東大寺続要録』宝蔵篇〕。破損した鏡は翌年3月14日、宝庫に戻される〔御物納目散帳〕 | ||
| 12月7日 | 先の盗難事件により紛失した宝物を確認するため、勅使が派遣され、中倉が開かれる〔『東大寺続要録』宝蔵篇〕 | ||
| 1237年 | 嘉禎3年 | 6月3日 | 宝庫を開いて宝物の点検が行われるも、周囲で不穏な動きがあり、倉中で櫃数を確認するに留まる〔『東大寺続要録』宝蔵篇〕 |
| 1239年 | 延応元年 | 11月26日 | 九条道家、勅封蔵を開いて鴨毛屛風、冠、玉箒など各種の宝物を見る〔「延応元年記」(『西園寺家記録』所収)、『東大寺続要録』宝蔵篇〕 |
| 1242年 | 仁治3年 | 3月13日 | 後嵯峨天皇の即位にあたり、勅封倉から玉冠と諸臣礼服・冠が出蔵される(これを基に即位式で着用の冠が新調された)。同月22日、宝物は勅封倉に戻されたが、一部は路次で破損した〔『東大寺続要録』宝蔵篇〕 |
| 1243年 | 寛元元年 | 閏7月23日 | 勅封倉の雨露による破損を修理するため、宝物を東大寺上司倉に移す〔『東大寺勅封蔵記』下〕 |
| 1246年 | 寛元4年 | 9月28日 | 勅封倉の修理が完了し、宝物が上司倉から戻される〔『東大寺続要録』宝蔵篇〕 |
| 1254年 | 建長6年 | 6月17日 | 北倉の扉に落雷し、一部の柱等が焼ける。すぐに修理に取りかかり、8箇日間で破損した部材が造り替えられる。7月6日、勅封蔵が開かれ、落雷による宝物の損失の有無が点検される〔『東大寺続要録』宝蔵篇〕 |
| 1258年 | 正嘉2年 | 1月22日 | 前関白の近衛兼経、勅封倉を開き、宝物を取り出して見る〔『東大寺続要録』宝蔵篇〕 |
| 1261年 | 弘長元年 | 9月5日 | 後嵯峨上皇、宝庫を開き、開眼筆、瑠璃壺等の宝物を取り出して見る。また、御袈裟を出蔵する。御袈裟は翌年8月21日に返納〔御物納櫃目録(続修後集三)、『東大寺続要録』宝蔵篇〕 |
| 1288年 | 弘安11年 | 4月23日 | 後深草上皇、勅封倉を開き、紫檀厨子、開眼筆等の宝物を見る〔『東大寺勅封蔵記』下〕 |
| この年、宝庫の屋根瓦が部分的に葺き替えられる〔正応二年正月十八日東大寺修理新造等注文案(東大寺文書) | |||
| 1328年 | 嘉暦3年 | 4月20日 | 宝庫が盗難に遭ったことを受け、この日に盗人と宝物の行方が占われる〔同月二十一日安部支清勘文〕 |
| 7月5日 | 後醍醐天皇、宝庫盗人を捕えた者に報賞を出すことを通達する〔同日綸旨(東南院六ノ四)〕 |
南北朝・室町時代
| 西暦 | 和暦 | 月日 | 事項(〔〕内は典拠史料) |
|---|---|---|---|
| 1360年 | 延文5年 | 2月13日 | 朝廷より琵琶の出蔵について申し入れがあるも、東大寺の衆徒はこれに反対する〔延文五年東大寺衆徒僉議事書〕 |
| 1385年 | 至徳2年 | 8月30日 | 足利義満、南都へ下向の折、宝物を東大寺尊勝院において見る〔『春日権神主師盛記』(至徳二年記)同日条〕 |
| 1429年 | 永享元年 | 9月24日 | 足利義教、南都へ下向の折、宝物を見る。碁石3つと沈香2切を拝領する〔『満済准后日記』同日条〕 |
| 1465年 | 寛正6年 | 9月24日 | 足利義政、南都へ下向の折、宝庫を開き、東大寺西室において宝物を見る。2種の香木から各3片を切る〔東大寺三倉開封勘例、『蔭涼軒日録』同日条〕 |
安土桃山時代
| 西暦 | 和暦 | 月日 | 事項(〔〕内は典拠史料) |
|---|---|---|---|
| 1574年 | 天正2年 | 3月28日 | 織田信長、大和国多聞山城に下向の折、勅許を得て宝庫を開き、蘭奢待、全浅香、碁局を多聞山城において見る。蘭奢待より2片を切る。その後、3倉とも開いて中に入る〔天正二年截香記〕 |
江戸時代
| 西暦 | 和暦 | 月日 | 事項(〔〕内は典拠史料) |
|---|---|---|---|
| 1603年 | 慶長8年 | 2月25日 | 宝庫修理のため、開封される。宝物は「二ツ蔵」(東大寺油倉)に移納された〔東大寺三倉開封勘例、実祐記〕 |
| 9月 | 徳川家康、宝庫の修理にあたり長持32箇を寄進する〔慶長櫃(中倉)〕 | ||
| 1610年 | 慶長15年 | 7月21日 | 宝庫に盗人が入る(ただし、盗難の事実が判明したのはその2年後のこと)〔実祐記〕 |
| 1612年 | 慶長17年 | 3月21日 | 宝物が売りに出ているとの情報があり、宝庫を調べると北倉の床が切り破られていた〔実祐記ほか〕 |
| 閏10月21日 | 宝庫に盗み入った犯人(東大寺僧3名と町人1名)が捕らえられる。事件を受けて、11月13日に宝庫が開封され、宝物目録が作成される〔実祐記、東大寺三蔵御宝物御改帳ほか〕 | ||
| 1663年 | 寛文3年 | 4月16日 | 東大寺衆僧、宝庫の開封を要望し、これを受けて8月19日、江戸幕府が宝庫3倉の修理を命じる〔『庁中漫録』七〕 |
| 1665年 | 寛文5年 | 10月9日 | 東大寺衆僧、宝庫の開封(及び宝物の点検)を再度要望する〔『庁中漫録』七〕 |
| 1666年 | 寛文6年 | 3月4日 | 宝庫が開封される。翌日より各倉宝物の点検。目録が作られる。7日に閉封〔『庁中漫録』七、寛文六年正倉院御開封之記〕 |
| 1693年 | 元禄6年 | 5月16日 | 宝庫が修理のために開封される。同月20日まで宝物を点検し、目録が作られる(正倉院文書の存在が確認される)。点検された宝物は、東大寺油倉へ仮納された。6月15日より7月13日まで、宝庫の修理〔正倉院御開封記草書、東大寺正倉院開封記、『庁中漫録』四十五〕 |
| 8月1日 | 東大寺油倉に仮納してあった宝物が宝庫に戻され、7日に閉封の儀あり。この開封中、鴨毛屛風等が修理され、また江戸幕府より宝物用の箱や櫃が寄進される〔正倉院御開封記草書、元禄櫃(中倉)〕 | ||
| 1830年 | 文政13年 | この年、宝庫の屋根が大破し、東大寺が修理を願い出る〔正倉院宝物御開封事書〕 | |
| 1833年 | 天保4年 | 10月18日 | 宝庫が修理のために開封される。宝物は四聖坊において点検され(24日まで)、東大寺の東南院宝蔵・八幡宮南宝蔵(旧油倉)と大湯屋に仮置される〔正倉院宝物御開封事書、天保4年10月18日正倉院御開封之記〕 |
| 1835年 | 天保6年 | この年、宝物の調査が行われる。前回開封(元禄)時の目録と、2年前の点検目録とが照合され、また写本の作成が行われる〔東大寺開闢領地御施入勅書古絵図出現之記、天保七年東大寺正倉院御宝物目録ほか〕 | |
| 1836年 | 天保7年 | 3月頃 | 正倉院文書が穂井田忠友の手により整理、編集される〔『観古雑帖』、『山城大和見聞随筆』〕 |
| 6月20日 | 宝庫が閉封される。3年近くに及んだ開封の間に、杉箱16口が新調される(徳川家斉による寄進)〔天保七年六月廿日正倉院御閉封記〕 | ||
| 1847年 | 弘化4年 | 3月10日 | 東大寺大勧進所、寺宝の開帳を行う。このとき二月堂に展示された宝物の中に鴨毛御屛風、天平古切御屛風、正倉院古文書などの正倉院宝物が含まれる。展示は4月29日まで〔東大寺宝物録〕 |
近現代
| 西暦 | 和暦 | 月日 | 事項(〔〕内は典拠史料) |
|---|---|---|---|
| 1872年 | 明治5年 | 8月12日 | 宝庫が開封される。政府の社寺宝物調査(壬申検査)により、蜷川式胤らが20日まで宝物を調査。23日、閉封 |
| 1875年 | 明治8年 | 3月1日 | 東大寺大仏殿での奈良博覧会(第1回)が開幕し(5月20日まで)、宝物も展観される。奈良博覧会での宝物展観は、明治9年、11年、13年にもあった |
| 3月10日 | 宝庫と宝物が政府の直接管理の下に置かれる | ||
| 1877年 | 明治10年 | 2月9日 | 明治天皇、四聖坊において宝物を見る。このとき蘭奢待を截る |
| 1879年 | 明治12年 | 12月 | 宝庫に棚架を設けて宝物を陳列する旨の申請が伊藤博文よりあり、翌年1月に許可される |
| 1882年 | 明治15年 | 8月 | 宝庫内の陳列用棚架が完成し、宝物を陳列する |
| 1883年 | 明治16年 | 7月 | 宝物の毎年の曝涼が制度化する |
| 1884年 | 明治17年 | 5月6日 | 宝庫と宝物の管轄省庁が、宮内省に一本化される |
| 1885年 | 明治18年 | 12月 | 宮内省図書寮の下に正倉院宝庫掛が置かれる |
| 1889年 | 明治22年 | 7月9日 | 宝庫の定期曝涼の際に、参観を許可することになる |
| 1892年 | 明治25年 | 6月 | 宮内省に正倉院御物整理掛が置かれる。宝物整理と補修の開始(御物整理掛は明治37年に廃止) |
| 1893年 | 明治26年 | この年、東大寺尊勝院経蔵(聖語蔵)と経巻約5千巻が皇室に献納される。建物は後年、現在位置に移建 | |
| 1908年 | 明治41年 | 1月 | 宝庫と宝物が帝室博物館の所管となり、5月に東京帝室博物館に正倉院宝庫掛が置かれる |
| 1913年 | 大正2年 | この年、宝庫の全面解体修理が3月21日から12月23日にかけて行われる | |
| 1914年 | 大正3年 | 9月16日 | 奈良帝室博物館に正倉院掛が置かれ、11月より古裂の整理が始められる |
| 1925年 | 大正14年 | 4月15日 | 正倉院宝物古裂類臨時陳列展が、奈良帝室博物館で開かれる(同月30日まで) |
| 1940年 | 昭和15年 | 11月5日 | 正倉院御物特別展観が、東京帝室博物館で開かれる(同月24日まで) |
| 1946年 | 昭和21年 | 10月21日 | 正倉院特別展観が、奈良帝室博物館で開催される(第1回正倉院展)(11月9日まで) |
| 1947年 | 昭和22年 | 5月3日 | 宮内府図書寮正倉院事務所が設置され、宝庫と宝物の管理が博物館から移管される |
| 1953年 | 昭和28年 | 3月 | 鉄筋コンクリート造の新宝庫(現在の東宝庫)が竣工する |
| 1962年 | 昭和37年 | 3月 | 西宝庫が竣工する。翌38年、宝物を西宝庫へ移納 |
| 1997年 | 平成9年 | 5月 | 宝庫(正倉院正倉)が国宝に指定される |
| 1998年 | 平成10年 | 12月 | 宝庫(正倉院正倉)が「古都奈良の文化財」の一つとして世界文化遺産に登録される |
| 2014年 | 平成26年 | 10月 | 平成23年8月から実施されていた宝庫(正倉院正倉)の改修工事が完了する。屋根瓦が全面的に葺き替えられ、小屋組も補強された |
【主要参考文献】
- 福山敏男「東大寺の諸倉と正倉院宝庫」(同著『日本建築史研究』、墨水書房、昭和43年)
- 和田軍一『正倉院案内』(吉川弘文館、平成8年)
- 橋本義彦『正倉院の歴史』(吉川弘文館、平成9年)
- 西洋子『正倉院文書整理過程の研究』(吉川弘文館、平成14年)
- 杉本一樹『正倉院―歴史と宝物―』(中央公論新社、平成20年)
- 『正倉院紀要』第38号(宮内庁正倉院事務所、平成28年)
第77回 正倉院展、2025